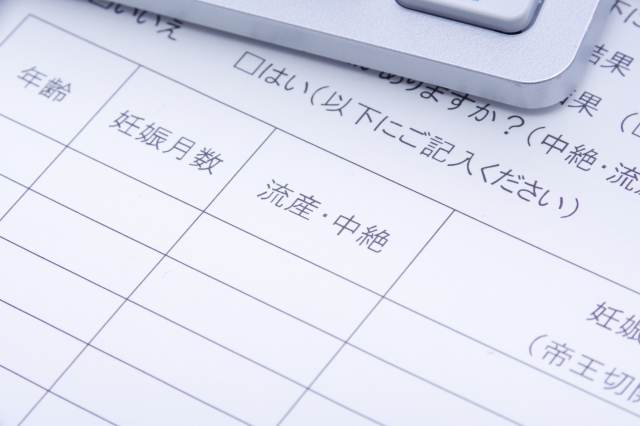妊娠初期の人工中絶について知っておきたいこと 〜医療機関での流れと注意点〜【医師監修】
- 2025年7月19日
- 更新日: 2025年9月29日
- 医療コラム
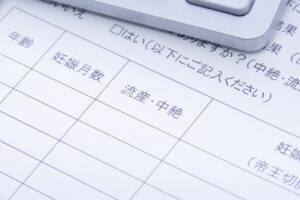
人工中絶を決断する理由はさまざま。それぞれ事情を抱えて決断する人工中絶ですが、身体的・精神的なリスクがあることを忘れてはいけません。
この記事では妊娠初期の中絶にはどのような方法があるのか、中絶をするまでの流れやリスクなど、人工中絶を受ける前に知っておきたい情報についてまとめています。
人工中絶は女性にとって大きな決断です。参考にして体と心に負担が少ない方法を選択していきましょう。
1. 妊娠初期の人工中絶はいつまで?

妊娠初期の人工中絶とは、妊娠12週未満に受ける中絶のことです。
一般的に妊娠初期は妊娠13週6日までですが、人工中絶の妊娠初期とは時期が異なるので注意しましょう。妊娠12週以降の中絶は「中期中絶」となり、中絶方法が初期とは違ったり、役所での手続きが必要になったりするほか体への負担が大きくなります。なるべく早い時期に中絶する方が、体への負担は少ないといえるでしょう。
手術での中絶をする場合、妊娠検査薬で陽性反応が出る妊娠4週以降から可能です。しかし妊娠超初期だと手術がむずかしいことがあるため、手術時期については受診した医療機関で相談しましょう。薬を使って中絶を希望する場合は、対象が妊娠9週までとなるため注意が必要です1)。
関連記事
2. 妊娠初期の中絶方法

中絶方法には大きく分けて手術と薬の2種類あります。手術には吸引法と掻爬(そうは)法があり、医療機関によって実施している方法が異なります。それぞれの特徴を理解して、希望する方法をおこなっている医療機関に受診しましょう。
1) 吸引法による手術
吸引法は細くて柔らかい管を子宮に挿入して、子宮のなかみを吸引する方法です。手術時間は10~15分ほどと短く、麻酔で眠った状態でおこなうため痛みを感じることはありません。体への負担が少ない手術法としてWHOでも推奨されており、近年多くの医療機関でおこなわれています。
吸引には電動と手動の2つの方法があります。
2) 掻把(そうは)法による手術
掻爬法は鉗子とよばれる器具を使って、子宮のなかみを掻き出す方法です。以前はこの方法が主流でしたが子宮を傷つけてしまうリスクが高く、近年では掻爬法を積極的におこなう医療機関は少なくなっています2)。しかし、必要時にはこの方法を行う場合もあります。
3) 薬による処置
日本では2023年に「経口中絶薬」が承認され、薬での中絶が可能となりました。承認されたばかりの薬でリスクや身体的・精神的負担の観点から、実施している医療機関がまだまだ少ないのが実情です。
経口中絶薬での中絶では、2種類の薬を時間差で服用します。1つめは妊娠の継続ができない状態にする薬、2つめは子宮を収縮させる作用のある薬です。人工的に子宮収縮を起こすことで、子宮のなかみを体外へと排出させます3)。
薬を使用しての中絶は一見手術よりも体への負担が少ないように感じるかもしれませんが、子宮が収縮する際に強い腹痛を感じ、大量に出血してしまうケースがあります。また子宮のなかみがすべて排出されないこともあります。日本ではまだ薬による中絶の件数が多くありません。実施している医療機関で説明を聞き、リスクなどを理解したうえで処置を受けるようにしましょう4)。
関連記事
3. 初期の妊娠中絶にかかる費用・相場とは?

基本的に中絶では健康保険が適用されません。自由診療となるため、クリニックによって中絶費用は異なります。
初期の妊娠中絶費用の目安は、手術でも薬でもおおよそ10~20万円程度です。このほかに診察代や検査代などが必要となります。また妊娠週数によって金額が異なる場合もあるため、詳しくは受診を検討している医療機関に問い合わせるのがよいでしょう。
4. 初期の妊娠中絶の流れと手順

1) 妊娠の確認
自宅で妊娠検査薬を使って妊娠を確認できますが、医療機関ではエコーで正確な妊娠週数を調べることができます。妊娠週数によって施術方法や費用が異なる場合があるため、中絶を検討したら早めに受診をしましょう。
2) 医療機関の選択と相談・受診
医療機関によって、おこなっている中絶の方法が異なります。自分が希望する中絶方法を実施している医療機関に受診しましょう。
受診の際に医師からは中絶方法の説明、費用やリスクなどについて説明があります。また中絶をするに当たって必要な検査があります。中絶は体と心への負担が大きいため、不安に思っていることや疑問を解消した状態で中絶が受けられるよう、医師としっかりと話をしましょう。
3) 必要な書類
人工妊娠中絶手術を受けるには、母体保護法に基づき同意書が必要です。同意書には本人と配偶者の署名・捺印が必要で、18歳未満の場合は保護者や親権者の同意・署名がなければいけません5)。
4) 手術/服用
中絶手術を受ける場合
麻酔をするため、前日から食事の制限があります。中絶を受ける医療機関からの指示を確認しましょう。
手術時間は10~15分程度です。手術前に点滴から麻酔をいれる静脈麻酔をするため、手術中に痛みを感じることはほとんどなく、眠っている間に手術が終了します。麻酔からしっかりと覚醒し、診察で問題がないと判断されたら帰宅となります。術後の安静やシャワー、仕事などについては病院から指示があるため、術後検診まではそれに従って生活しましょう。
薬による中絶を受ける場合
薬で中絶をする場合、医師の目の前で2種類の薬を服用します。まず1つめに妊娠の継続ができなくなる薬を服用し、決められた日時に2つめの子宮を収縮させる薬を服用します。薬を飲む前後の生活に制限がある場合があるため、受診する医療機関に確認しましょう。
2つめの薬は子宮を収縮させる作用があるため、服用後に強い腹痛を感じます。子宮のなかみが排出されたことを確認後、医師が診察をし問題ないと判断されたら帰宅となります。
5) 術後診察
術後診察では子宮のなかに胎嚢などが残っていないか、子宮がしっかりと収縮しているか、術後の感染がないかなどをチェックします。子宮の回復状態によっては複数回の診察が必要な場合もあります。
5. 初期の妊娠中絶に伴うリスク

1) 身体的リスク
中絶手術での身体的リスクは大量出血や感染症のほか、子宮を傷つけてしまい穴があいてしまうことがあります。
これらのリスクを回避するために薬での中絶を選択する人もいるかもしれません。しかし薬での中絶では強制的に子宮を収縮させることによる強い痛みがあります。さらに子宮のなかみがすべて出てこないことがあり、その場合は手術を行う必要が出てきます。
中絶の方法によって身体的リスクに違いはありますが、どちらのリスクも承知した上で施術方法を選択していきましょう。またリスクを最小限に抑えるために、経験豊富な医療機関を選び適切なケアを受けましょう。
2) 心理的リスク
中絶後には精神的なストレスから心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状があらわれる「中絶後遺症候群(PAS)」になることがあります。不眠や抑うつ状態、情緒不安定といった精神的な症状だけでなく、頭痛や吐き気、めまいといった身体的な症状が出ることもあります。
中絶後は体と心を休ませ、つらい気持ちは家族や信頼できる友人に打ち明けることで一人で抱え込まないようにしましょう。カウンセリングや心の専門医へ相談することで中絶後遺症候群を予防・解消できることもあります。中絶後は自身の心を守るために、周囲へサポートを求めることも大切です6)。
まとめ:初期の人工中絶でも母体への負担がかかる
中絶はどの方法を選択しても、体と心への負担が大きい施術です。なるべく母体への負担を少なくしたいと考えたら、妊娠が分かったら早めに医療機関へ相談しましょう。
また中絶後は心への負担があることも忘れずにいてください。体だけでなく心も休めてあげること、つらい気持ちを押し込めないことが、中絶後遺症候群の予防には大切です。自身の心と体を大切にして、安全な中絶を選択していきましょう。
関連記事
安心・安全に出産を迎えるために、個別栄養相談、助産師外来、母親学級、マタニティビクスなど多種多様なメニューを設けております。

詳しくはこちら
ガーデンヒルズウィメンズクリニック 各種教室の案内
参考文献・参考サイト
1)日本産婦人科医会 人工妊娠中絶をお考えの方へ
2)日本産婦人科医会 安全な人工妊娠中絶手術について
3)ラインファーマ株式会社 メフィーゴ®パック(薬)とは
4)厚生労働省 いわゆる経口中絶薬「メフィーゴパック」の適正使用等について
5)母体保護法
6)人工妊娠中絶後の心のケアの在り方に関する研究
この記事の監修
牛丸敬祥 医療法人 ガーデンヒルズウィメンズクリニック院長

経歴
- 昭和48年 国立長崎大学医学部卒業
- 長崎大学病院産婦人科入局。研修医、医員、助手、講師として勤務。
- 産婦人科医療を約13年間の研修。体外受精に関する卵巣のホルモンの電子顕微鏡的研究
- 医療圏組合五島中央病院産婦人科部長、国立病院 嬉野医療センター産婦人科部長
- 長崎市立長崎市民病院産婦人科医長、産科・婦人科うしまるレディースクリニック院長
- 産婦人科の他に麻酔科、小児科の医局での研修
- 産婦人科医になって51年、35,000例以上の出産、28,000例の硬膜外麻酔による無痛分娩を経験しています。