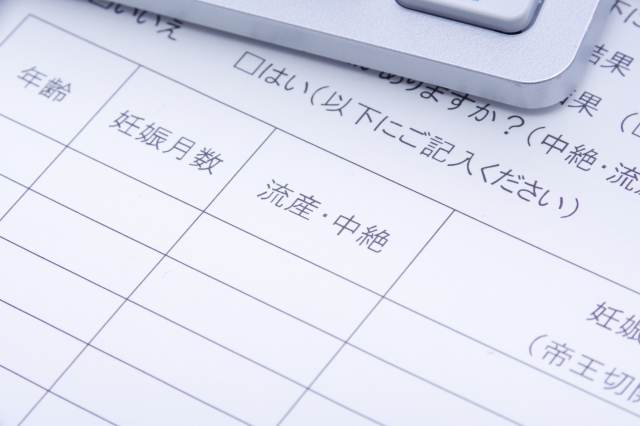妊娠中期の人工妊娠中絶(中期中絶)について知っておきたいこと【医師監修】
- 2025年8月9日
- 更新日: 2025年7月28日
- 医療コラム

妊娠中期の人工妊娠中絶を決断する方には、さまざまな理由があるでしょう。この記事では妊娠中期の中絶について知っておいてほしいことをまとめています。
妊娠中期の中絶は心と体への負担が大きい手術です。さらに妊娠初期の中絶とは異なり手術後にはやらなければいけない手続きもありますのでチェックしていきましょう。
1. 妊娠中期の中絶とは?「何週から」「いつまで」?

妊娠中期の中絶の期間は、母体保護法によって「妊娠12週以降、22週未満」と定義されています。妊娠22週を過ぎてしまうと、人工妊娠中絶は受けられなくなるため注意しましょう。
妊娠初期の中絶と、妊娠中期の中絶では大きく異なります。妊娠初期と中期の中絶の違いはこちら。
| 中絶の時期 | 受けられる期間 | 手術方法 | 死亡届け・埋葬 |
| 初期 | 妊娠11週6日まで | 吸引法・掻爬(そうは)法、薬による中絶 | 必要なし |
| 中期 | 妊娠12週0日~21週6日まで | 出産と同じ方法 | 必要 |
中期中絶では出産と同じ方法での手術となるため、体への負担が大きいといわれています。また術後は役所への届け出と埋葬が必要となるため、身体的にも精神的にもストレスが大きいでしょう。妊娠中期の人工妊娠中絶手術が受けられる医療機関は限られています。さらに妊娠週数が長くなるほどに心身の負担が大きくなるため、中絶の意思がある方は早めに受診をしましょう1)。
関連記事
2. 妊娠中期の中絶の流れ、医療機関での手順

妊娠中期の中絶の流れについては、妊娠週数や母体の状態、医療機関によって異なります。そのため、ここでは一般的な流れと手順について紹介していきます。
1) 事前カウンセリングと検査
中絶手術を受ける前に、まずは正確な妊娠週数を知るために超音波検査などの検査をしていきます。
産婦人科医から手術方法や当日の流れ、リスクなどについての説明と事前カウンセリングを受けます。中期の中絶は心身ともに負担の大きい手術です。事前カウンセリングで疑問を解消し、不安が少ない状態で手術を受けられるようにしましょう。
医師からの説明を受けて中絶を希望する場合は、血液検査などの手術に必要な検査をおこないます。
2) 人工妊娠中絶「分娩形式」の具体的な流れ
中期の中絶は、出産と同様に陣痛を起こして赤ちゃんを娩出します。入院期間は2~4日程度です。
手術前日は子宮の入り口を広げるための処置をおこない、手術当日は陣痛誘発剤を使って人工的に陣痛を起こして赤ちゃんを娩出します。術後診察で経過が問題ないことを確認してから退院となります。
入院のタイミングや入院期間、手術方法については医療機関によって異なるため、詳細については受診する医療機関に確認しましょう。
3) 術後の経過とケア
中期中絶は母体への負担が大きい手術です。そのため手術後、退院後は医師の指示に従って安静を守り、術後の定期検診は必ず受けましょう。退院後の術後検診では子宮が正常に戻っているか、経過が順調かを確認します。
術後に注意したいのが感染です。医師から許可が出るまでは入浴は避け、シャワーでしっかりと清潔を保ちましょう。出血がある期間はこまめにナプキンを交換するのも、感染予防のために大切です。
手術後は子宮が元に戻ろうとして収縮する痛みがあります。鎮痛剤を処方された場合は、薬を飲んで様子をみましょう。薬を飲んでも痛みがおさまらなかったり大量に出血があったりするときは病院に相談しましょう。
3. 妊娠中期の中絶に伴うリスクと合併症

どの時期の中絶においても、精神的なリスクは避けられません。しかし身体的な負担は初期よりも中期の方が大きいといわれています。ここからは中期中絶に伴う心身のリスクと合併症について解説していきます。
1) 身体的リスク
妊娠中期の中絶は、妊娠週数が進んでいることによる体の変化、手術による負担から身体的リスクは妊娠初期に比べて高いといわれています。妊娠中期の中絶による主な身体的リスクはこちらです。
出血
中絶手術の際に子宮が傷つき出血してしまうことや、胎盤などの組織の一部が残ってしまうこと、術後に子宮が十分に収縮しないことなどが原因です。大量に出血してしまったり出血がいつまでも続いてしまったりして不安な時は、手術を受けた医療機関に相談しましょう。
感染症
中絶手術前の子宮を広げる処置で感染することがあります。ほかにも術後の清潔が保たれていないと感染のリスクが高くなってしまいます。熱が出る、痛みがあるなどの症状があるときは、早めに医療機関に相談しましょう。
子宮内膜損傷
妊娠週数が進むと徐々に子宮が大きくなり、子宮内膜は薄くなります。薄くなった子宮内膜を手術の際に傷つけてしまうことがあるのです。損傷が軽度であれば予後はよいといわれていますが、重度になると受精卵が着床しづらくなってしまうこともあります。
将来の妊娠への影響
中絶手術で気になるのが「将来の妊娠のこと」だという人も多いでしょう。「不妊になるのではないか?」「妊娠出来ても無事に出産するのがむずかしいのではないか?」そんな不安や疑問を持つ人もいるでしょう。
中期の中絶では子宮内膜を損傷するリスクがあり、このことから将来妊娠した際に早産のリスクが高くなる可能性があるといわれています。しかし必ずしも不妊になるわけではないため、術後の検診をしっかり受けて次の妊娠に備えることが大切です。
2) 精神的リスク
中絶はどの時期においても精神的なストレスを受けやすいですが、中期中絶では初期よりも心への負担が大きいといわれています。
赤ちゃんへの罪悪感や妊娠・手術への後悔、悲しみ、喪失感から精神的に不安定になりやすいのです。「中絶後遺症」とよばれる心的外傷後ストレス障害(PTSD)の症状があらわれることもあります。不眠や抑うつ状態、情緒不安定といった精神的な症状だけでなく、頭痛や吐き気、めまいといった身体的な症状が出る人もいるでしょう。
中絶手術後は心身の回復を優先に、十分な休息をとるようにしましょう。家族や信頼できる友人につらい気持ちを打ち明けたり、ときには専門家の力を借りることも大切です。婦人科や心療内科、カウンセリングなど、専門家があなたに合った適切なサポートをしてくれますよ2)3)。
4. 中絶後の手続き「死亡届」について

妊娠12週以降に中絶手術を受けた場合、7日以内に「死亡届」の提出が必要です。医療機関が発行する「死産証書」を持参して、市区町村の役所で手続きをおこないましょう。なお中絶手術の場合は、死亡届を提出しても戸籍に記載されることはありません。
中期中絶では死産届のほかに、赤ちゃんの埋葬も義務付けられています。死産届け提出後に「火葬許可証」が役所から発行されるため、葬儀社で手続きをして赤ちゃんの火葬をおこないます。
心身が万全ではない状態で、これらすべてを1人でおこなうのは大変です。死亡届を代理人に提出してもらう、医療機関から葬儀社を紹介してもらうなど、家族やパートナーの手を借りておこなっていきましょう。
5. 妊娠中期の中絶にかかる費用

人工妊娠中絶は健康保険が適用されない自費診療であること、そして母体の状態や妊娠週数によっておこなわれる処置に違いがあることから、中絶費用は一律ではありません。くわしい料金については受診予定の医療機関に確認しましょう。
まとめ:中期中絶は心と体に負担が大きい手術
中絶は妊娠週数が進むにつれて体の負担が大きい手術です。さらに中期の中絶手術をおこなっている医療機関も少ないため、中絶を意識したら早めに受診をしましょう。
中絶は決断するまで、そして決断した後も心と体に大きな負担がかかります。さらに中絶後には役所への届け出、埋葬もあり、心と体が休まる時間がありません。中絶手術を受ける方は周りのサポートをしっかりと受けて、ときには専門家に頼って心と体の回復を最優先にしましょう。
関連記事
安心・安全に出産を迎えるために、個別栄養相談、助産師外来、母親学級、マタニティビクスなど多種多様なメニューを設けております。

詳しくはこちら
ガーデンヒルズウィメンズクリニック 各種教室の案内
参考文献・参考サイト
1)母体保護法
2)日本産婦人科医会 安全な人工妊娠中絶手術について
3)人工妊娠中絶後の心のケアの在り方に関する研究
この記事の監修
牛丸敬祥 医療法人 ガーデンヒルズウィメンズクリニック院長

経歴
- 昭和48年 国立長崎大学医学部卒業
- 長崎大学病院産婦人科入局。研修医、医員、助手、講師として勤務。
- 産婦人科医療を約13年間の研修。体外受精に関する卵巣のホルモンの電子顕微鏡的研究
- 医療圏組合五島中央病院産婦人科部長、国立病院 嬉野医療センター産婦人科部長
- 長崎市立長崎市民病院産婦人科医長、産科・婦人科うしまるレディースクリニック院長
- 産婦人科の他に麻酔科、小児科の医局での研修
- 産婦人科医になって51年、35,000例以上の出産、28,000例の硬膜外麻酔による無痛分娩を経験しています。